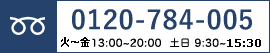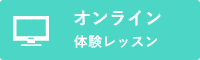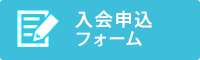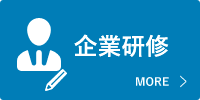速読ブックレビュー・書評
木村インストラクター書評『何者』
朝井 リョウ (著)
286ページ
就活の情報交換をきっかけに集まった、拓人、光太郎、瑞月、理香、隆良。学生団体のリーダー、海外ボランティア、手作りの名刺…… 自分を生き抜くために必要なことは、何なのか。影を宿しながら光に向いて進む、就活大学生の自意識をリアルにあぶりだす、書下ろし長編小説。
【読書の所要時間】 1回目 2時間(熟読)、2回目 2時間(熟読)
先月の書評、『桐島、部活やめるってよ』で「予告」した通り、朝井リョウさんの最新作『何者』を手に取ってみました。そうなんです。あれ、「予告」のつもりだったんですよ。未読の方は、私の『桐島~』書評もぜひ。
それはさておき、今回の『何者』。主人公は6人の大学生。うち4人は就職活動に悪戦苦闘。残る2人はそこから一歩距離を置き、執筆活動や舞台演劇に粉骨砕身。この6人。6人が6人ともツイッターやってるんですね。ここがミソ。
ツイッター。年配の方ご存知ですか? 若い人たちが、インターネット上でああでもないこうでもないと、日々の由なしごとをブツクサつぶやくあれです。色んな人の独白がポロポロ漏れ聞こえてくる。それがツイッター。就活の切実な悩みをぶつけ合っている子が、目の前にいるその子が、ツイッターでは全然違うことをつぶやいている。人と喋りながら、同時進行でケータイから別内容をツイートする(=つぶやく)。ツイートできてしまう。テクノロジーの進歩が若者文化にもたらした影響力。これがものの見事に反映された小説です。
この小説を読み解くカギ。それは、ツイッターと就職活動の類似性ですね。ツイッターと就活(=就職活動)って似てるんですよ。どこが似てるか。どちらも「何者」かにならなくてはいけない。短文で自己アピールしなくてはいけない。ツイッターは字数制限ありますから。ツイ-ト1回あたり140文字まで。ね? 就活の課題みたいじゃないですか。
もっと本質的な類似点。どちらも見栄っ張りです。自分を良く見せたい。良く見せなくてはいけない。企業のツイッターは別として、ツイッターやってる個人には、正直者もいれば、「カッコつけたがり」もいる。「本音用」と「建前用」で、2つのアカウント(=個人名)を使い分けてる人もいるぐらい。小説に登場する6人の大学生も、何人かはそうしているようで。
就職活動は大変です。大人物でないとわかっていながら、さも大人物であるかのように印象付けなくてはいけません。かつて私も就活に必死でした。なので、小説に出てくる就活生が抱える悩みや焦りは理解できるんですよ。主体性も自発性もなくて、大きなうねりに飲み込まれて流されてるだけじゃないのか。そんな茫漠たる不安にさいなまれる日々。でもやるしかないんだ。そう言い聞かせて自分を奮い立たせる毎日。私にもありました。
一方で、敢えて就活しない道を選んで、外野から冷ややかに眺める大学生の心情にも共感できます。小説に出てくる宮本隆良という大学生が、ちょうどそういうタイプ。みんなと同じ格好をして、みんなと同じ組織の歯車に組み込まれていく。それだけはゴメンだね。オレはオレ。独立独歩の気風というか気概というか。いやあ、これもよくわかる。
ただ、今の時代は、私の就活中には影も形もなかった、お手軽でお気軽なツイッターがあります。自分を精いっぱい飾り立てようと思えば、いくらでも飾り立てられるわけです。ツイッターで、人は「何者」にでもなれる。けれど実のところは「何者」でもない。「何者」にでもなれる特権を得た現代人は、にもかかわらず自分が「何者」かに迷っている。自分で自分の正体が見えない。わからない。つかめない。カメレオンみたい。それって、就職活動特有の苦悩でもあるわけで。ツイッターという便利なメディアの存在が、就活中の学生の苦悩を、以前にも増して深刻なものにしている。そんな見方もできます。
そういえば、著者の朝井リョウさん。大学在学中に『桐島~』で文学賞を獲得し、売れっ子作家の仲間入りを果たしながら、どういうわけか一般企業に就職。サラリーマンとの兼業を選択しているではありませんか。恐らくはこの小説、朝井さんの偽らざる実感と実体験に基づくものでしょう。私と同じで、就活するしかない学生の立場にも、就活しない進路を選択する学生の立場にも立てる。彼のどっちつかずで曖昧なポジションと、「何者」かになれそうでなれないツイッターの存在が、この小説を生んだと言えそうです。
とはいえ、人は迷う生き物ですから、それでいいのかもしれません。いつだって人は悩み、苦しみ、あがいて、もがいてきました。就職活動があろうとなかろうと、ツイッターの存在があろうとなかろうと、人としての宿命からは逃れられない。たまたま学生諸君が就活の時期にぶち当たり、たまたま今という時代にツイッターが台頭してきただけであって、それらと上手く付き合えるかどうかは、1人1人の心がけにかかっています。そういう意味では、極めて現代的であると同時に、極めて普遍的な小説なのです。
何より、悩みは文学の源泉です。これ以上ない「ネタ元」。素材供給源。朝井リョウという作家は、恐らくたった今、悩みの渦中にいるのでしょう。けれども、悩みのない世界に文学は必要とされないし、産声を上げるはずもない。そういう意味で、この悩みは大いに歓迎してやらなくてはいけない。そんな気がします。唐突に訪れるエンディングにも、私と同じに考えているであろう作者の心境が、よーく表れています。まあ読んでみて下さい。「ははーん、そういうことね」と膝を打ちますよ。
苦しみの向こうにある小さな喜び。暗闇の彼方にチラリとのぞく光明。明けない夜はない。実に朝井リョウさんらしい一冊でありました。
(木村インストラクター 2013年4月)
速読ブックレビュー・書評
辻インストラクター書評『遠野物語―付・遠野物語拾遺』
柳田 國男 (著)
268ページ
かつての岩手県遠野は、山にかこまれた隔絶の小天地で、民間伝承の宝庫だった。柳田国男が民間伝承の宝庫でもあった遠野郷で聞き集め、整理した数々の物語集。日本民俗学を開眼させることになった「遠野物語」は、独特の文体で記録され、優れた文学作品ともなっている。
【読書の所要時間】 2時間(熟読で1回)
岩手県に遠野という街があります。民話で有名な所です。岩手の山深い地勢において、僅かな平地を見つけて点々と連なる諸都市の並びからはやや孤立し、山中の盆地に位置する街です。(岩手の地図を見れば一目瞭然ですが、岩手の諸都市の並びにはわかりやすい規則性があります。海岸沿いに陸前高田・大船渡・釜石・宮古など震災関係で耳にする街々が縦に並び、内陸では県中央を南北に伸びる狭隘な平地に一関・北上・花巻・盛岡などが等間隔に連なります。それ以外は山地です。そして遠野はまさにその山地に位置しています。)
今は民話の町として栄える遠野ですが、その源流となったのがこの『遠野物語』です。著者は柳田国男という人で、日本の民俗学の創始者として有名です。発行は明治四十三年。遠野に伝わる民話や伝説・習俗を柳田国男が人づてに聞き、書き留めたもので、一種の民話集のような趣を持っています。
現代でこそ古典として扱われつつある『遠野物語』ですが、内容においては重要な知識も教養も与えてくれることはありません。河童やザシキワラシなど、現代にも名の通った物の怪もいくつか登場こそします。しかし大方は遠野土着の名も知らぬ伝説や習俗に終始しており、民俗学という分野に入れ込む人、遠野という土地に何らかの縁のある人でなければ興のそそられようがないかも知れません。
いくつか短い例をあげましょう。
「四十 草の長さ三寸あれば狼(おいぬ)は身を隠すといへり。草木の色の移りゆくにつれて、狼の毛の色も季節ごとに変はりてゆくものなり。」
「九八 路の傍に山の神、田の神、塞(さえ)の神の名を彫りたる石を立つるは常のことなり。また早池峰山六角牛山の名を刻したる石は、遠野郷にもあれど、それよりも浜にことに多し。」
終始このような感じです。一口に「狼は毛の色が変わる」「アニミズム的な石碑が多くある」と言ってしまえば身も蓋もなく、また事実それ以上のことはまるで語られていません。本編は文庫本にして80ページたらず、119の小エピソードがただただ並置されているのみで、作りはこれ以上なく簡素なものです。構成も文体も野ざらしのままで、作為の影など一切顔を出しません。そういった形式の中で紹介される種々の伝説も、紹介、というよりはまるで独りごちるかのように、ただ 訥々と語られてゆくのみです。
したがって、この本から何かを得ようとする試みは空を掴むでしょう。現代的な知見はもちろん入っておらず、時代に左右されることなく通用する思想といったものも、一読しただけで掴み出すのは困難でしょう。実用的な知識、社会を生き抜く手練手管、それどころか日常的な生活の知恵というほどの内容すら込められていません。話はおよそ荒唐無稽とよんで差支えないもので、夢と現実を行き来しているような印象すら与えます。さりとて、小説を読むような娯楽性を求めるには枯淡に過ぎます。味気ないのです。ストーリーは多く山なしオチなしで、起承転結もはっきりせず、ぶつ切りな印象すら与える場合が多々あります。
「三四 白望(しろみ)の山続きに離森(はなれもり)といふ所あり。その小字に長者屋敷といふは、全く無人の境なり。ここに行きて炭を焼く者ありき。ある夜その小屋の垂れ菰(こも)をかかげて、内を窺ふ者を見たり。髪を長く二つに分けて垂れたる女なり。このあたりにても深夜に女の叫び声を聞くことは珍しからず。」
この完結した一つの話から、なんとなく不気味な印象以外のいかなるものも得られようがないではないでしょうか。
では『遠野物語』は無用の書なのでしょうか。読書に実用的な知識を求めている限りではそう言えるかも知れません。この進んだ時代に、今さら「山神山人の伝説」もないでしょう。しかし柳田国男が序文にて「願はくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。」と語った通り、『遠野物語』にはある種の戦慄を催させるような凄みがあります。ぶっきらぼうな、枯れたような語り口でいてしかしその中に、淡いものですが、豊かな情趣が確かに潜んでいると感じさせるのです。
“無用の用”といった難しく曖昧な概念を振り回す必要はありません。『遠野物語』に籠められている味わいのようなものは、この本に有用性や、穿ったような解釈などをこちらから押し付けようとしない限り、誰にも感じられるものに思います。この本に関しては何かを得よう、何かに役立てようという心意気自体が読書を欺きかねません。現代に通用する内容や合理性を求めることはお勧め出来ません。本文は、そういった考え方とは真逆の考え方で満たされているからです。興奮や感情移入といった刺激、感情を波立たせるような娯楽性を求めるのもおそらく無益でしょう。「何が言いたいのかわからない」といった批判も的外れでしょう。テーマ性などという重厚な概念が、この本にとって余計な装飾以上の意味を持つとも思えません。もちろん、教養人必携といった大層な見方とも合いうことはなさそうです。『遠野物語』に関する限り、読書にはある種の虚心坦懐を必要とします。疲れた時に何とはなく風景に目をやり、例えば山を見て、その姿が心に沁みるといった誰でも持つ経験と同種の精神を必要とするのです。一種の詩情が求められるように思います。
確かに現代では珍しい本と言えるかも知れません。その事情は発刊当時も変わらなかったらしく、柳田国男の手になる序文は自虐に満ちています。「思ふにこの類の書物は少なくも現代の流行にあらず。」「自己の狭隘なる趣味」「今の事業多き時代に生まれながら、問題の大小をもわきまへず」などです。しかし直後に柳田は力強く開き直りを見せています。「はて是非もなし。この責任のみは自分が負はねばならぬなり」。
『遠野物語』に含まれる夢幻性を、現実的でなく、合理性がなく、したがって何の役にも立たないと断ずる方には、柳田国男の次の言葉が一つの指針になるかも知れません。「要するにこの書は現代の事実なり」。この一言で表現された、『遠野物語』の幻想趣味的な世界を遠野の“事実”と断定的に言い切り、そこに一つの楽しみを発見した柳田国男の信念こそ、この本の無類の価値と結びついているのではないかと感じます。
そういった意味では、全ての方にお勧めしてみたい本です。「無意味な本だ」「退屈だ」といった感想を持たれる方はおそらく多いでしょう。しかし、無意味で退屈なのは本の方なのか、はたまた自分自身なのか、わかったものではないでしょう。
(辻インストラクター 2012年4月)